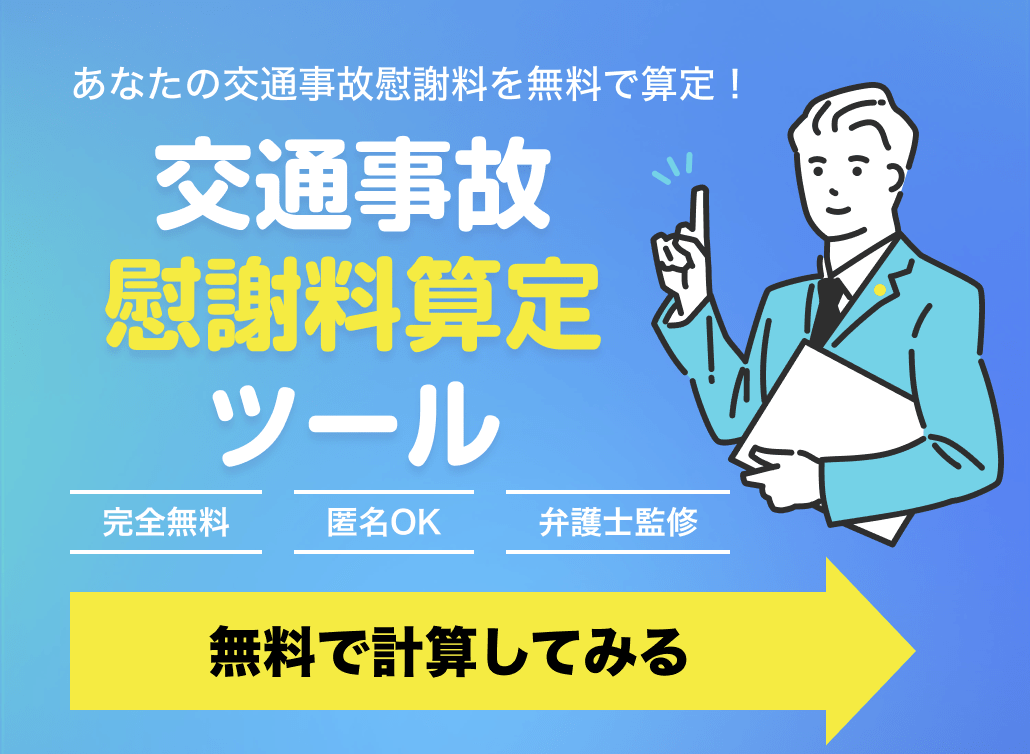もらい事故なのに過失あり? 納得できないときに行うべき対応
- その他
- もらい事故
- 対応

高崎市が公表している交通事故発生状況に関する統計資料によると、令和3年の高崎市内で起きた交通事故の発生件数は、2310件でした。負傷者数は2862人で、死者数は11人であり、いずれも前年よりも増加しています。
交通事故は、自分自身でどんなに気を付けていたとしても相手の過失によって生じることがあります。たとえば、停車中に追突されたというケースです。このようなもらい事故にあった場合には、被害者の保険会社では示談の代行をしてもらえないので、加害者や加害者の保険会社との交渉はすべて被害者ご自身で行わなければなりません。
そのような状況で加害者の保険会社から「あなたにも過失がある」と言われた場合にはどのように対応したらよいのでしょうか。今回は、もらい事故で「過失あり」と言われた場合の対応について、ベリーベスト法律事務所 高崎オフィスの弁護士が解説します。
1、過失割合がゼロになるもらい事故とは
もらい事故とはどのような事故類型になるのでしょうか。以下では、もらい事故の基本的事項と過失割合がゼロになるもらい事故の具体例について説明します。
-
(1)もらい事故とは
もらい事故とは、被害者側に一切過失のない事故のことをいいます。過失割合がないということは、交通事故による損害を請求する際に、過失割合に応じた減額はありませんので、生じた損害のすべてを請求することができます。
一般的に、交通事故が発生した場合には、事故類型に応じて過失割合が定められることになります。そのうえで保険会社に連絡して保険会社の担当者が加害者側と交渉をするのが一般的です。しかし、もらい事故のように被害者に過失がない場合には被害者側の保険会社は示談交渉を行うことができません。そのため、もらい事故では、被害者自身が加害者側と示談交渉を行わなければならないという特徴があります。 -
(2)過失割合がゼロになるもらい事故の例
過失割合がゼロになるもらい事故の具体例としては、以下のケースが代表的です。
① 信号待ちで停車中に追突されたケース
赤信号や一時停止の規制に従って停車していたり、渋滞を理由で停車している車に追突したりした場合には、追突車両の前方不注視や車間距離不保持などの一方的な過失によるものといえます。したがって、追突された被害者の過失はゼロが原則となります。
② センターラインオーバーの対向車と正面衝突したケース
車を運転する際には、道路の中央線から左の部分を通行しなければなりません。そのため、左側部分を通行する車とセンターラインオーバーをした車が正面衝突した場合には、原則としてセンターラインをオーバーした車の一方的な過失によるものといえます。したがって、このケースでは、被害者の過失割合はゼロが原則となります。
③ 青信号で交差点を進行中に信号無視した車と出合い頭で衝突したケース
信号機が設置されている交差点では、信号機に従って進行しなければなりません。そのため、青信号で交差点に進入した車には過失は認められません。この場合には、信号を無視して交差点に進入した車の一方的な過失によるものといえますので、被害者の過失割合はゼロが原則となります。
2、もらい事故で請求することができる賠償金
もらい事故の被害に遭った場合には、以下のような損害を請求することができます。
-
(1)物損事故の場合
もらい事故にあったものの、怪我などがない場合には、物損事故として以下の損害を請求することができます。
① 車の修理費
車の修理が可能である場合には、車の修理に要した費用のうち、必要かつ相当な費用について請求することができます。ただし、車の時価が修理費を下回る場合には、車の時価額までしか請求することができません。
② 評価損
車が破損すると修理をしたとしても完全に元通りになるとは限りません。車の機能に欠陥が残ってしまったり、修理歴が残ったりすることによって売却時の評価額が下がることもあります。
このような場合には、その差額分について評価損として請求することができる場合があります。ただし、評価損は、常に認められるものではなく、新車や高級車などの場合に限られ認められる傾向にあります。
③ 代車使用料
車を修理に出す場合には、その間は車を使用することができませんので、レンタカーなどを利用することになります。レンタカーを利用する必要性があり、その期間が相当なものであれば、その費用については代車使用料として請求することができます。 -
(2)人身事故の場合
もらい事故によって、怪我をしてしまったという場合には、上記の物損事故の損害に加えて、以下の損害を請求することができます。
① 治療費
怪我の治療のために必要かつ相当な費用について請求することができます。ただし、請求することができる治療費は、症状固定日までの部分に限られます。
② 通院交通費
電車やバスを利用した場合には、全額を請求することができますが、タクシーを利用した場合には、タクシー利用の必要性が認められなければタクシー料金を請求することができません。
自家用車を使用した場合には、ガソリン代などの実費を請求することができます。
③ 休業損害
入通院のために仕事を休んだ場合には、その期間の給料が減ることになります。このような減収分については休業損害として請求することができます。
休業損害は、会社員や自営業者だけでなく主婦も請求することができます。
④ 逸失利益
交通事故により後遺障害が生じた場合には、労働能力の低下によって将来得られる収入が減少してしまいます。このような場合には、逸失利益として本来得られるはずの収入を請求することができます。
⑤ 慰謝料
交通事故による慰謝料には、「傷害慰謝料(入通院慰謝料)」と「後遺障害慰謝料」の2つがあります。交通事故によって入通院を余儀なくされた場合には、入通院期間や入通院実日数などを基準として傷害慰謝料を請求することができます。また、交通事故によって後遺障害が生じてしまった場合には、障害の内容および程度に応じて後遺障害慰謝料を請求することができます。
3、相手の保険会社に「あなたに過失がある」と言われたら
もらい事故であるにもかかわらず相手の保険会社から「あなたに過失がある」と言われた場合にはどのように対応したらよいのでしょうか。
-
(1)証拠を提示して反論する
もらい事故は、被害者側に一切過失がない事故であるにもかかわらず、相手の保険会社から被害者にも過失があると言われてしまうことがあります。
このような場合には、自己に過失がなかったことを裏付ける証拠を提示して反論していく必要があるでしょう。利用できる証拠としては、ドライブレコーダーの映像、目撃者の証言、実況見分調書などがあります。また、民間企業に科学的な鑑定を依頼して事故状況を明らかにするという方法もあります。 -
(2)民事裁判を起こす
被害者と保険会社の担当者との話し合いでは、過失割合が決まらないという場合には、最終的に民事裁判を起こして、裁判所に判断をしてもらうことになります。
民事裁判では、過失の有無については、当事者の主張とそれを裏付ける証拠によって状況が判断され、判決が下ります。民事裁判は、専門的かつ複雑な手続きですので、自己の主張を適切に裁判に反映さえるためにも弁護士に依頼をして進めることをおすすめします。
4、弁護士に対応を依頼したほうがよいケース
以下のようなケースでは、ご自身で進めるのではなく弁護士に依頼をして進めることをおすすめします。
-
(1)過失割合に争いがあるケース
もらい事故のケースでは、被害者側の保険会社が示談交渉を行ってくれません。したがって、被害者自身で対応する必要が出てきます。事故によって心身ともにダメージを受けているときであればなおさら、相手の保険会社の言い分が正しいかどうかを判断することができず、不利な過失割合で示談に応じてしまうリスクがあるといえるでしょう。
このような場合には、弁護士に依頼をすることによって、弁護士が被害者に代わって示談交渉を進めることが可能になります。もらい事故であることを裏付ける証拠についても弁護士が収集することができますので、被害者の負担を大幅に軽減することができます。 -
(2)慰謝料を請求するケース
慰謝料の算定基準には、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判基準(弁護士基準)の3つがあります。一般的に自賠責保険基準が最も金額が低くなる基準で、裁判基準が最も高くなる基準だといわれています。
被害者としては、少しでも実態に適した慰謝料をもらいたいはずです。しかし、慰謝料が高額になる裁判基準によって算定した慰謝料を請求することができるのは、弁護士が示談交渉をする場合か裁判を起こした場合に限られます。被害者自身の交渉では、裁判基準による慰謝料を請求することはできません。
入通院状況や後遺障害の有無・程度などによって、慰謝料の金額は2倍以上もの差が生じることがありますので、どの算定基準を採用するかが非常に重要となります。少しでも法的に適切な金額の慰謝料を請求したいと考えるのであれば、弁護士への依頼をおすすめします。 -
(3)弁護士費用特約に加入しているケース
弁護士に依頼をするときに不安になるのが費用面の問題です。交通事故の賠償金をもらったとしても弁護士費用を支払わなければならなくなると、弁護士に依頼をする実益があまりないとお考えの方も少なくないでしょう。
そのようなお悩みを抱えているときは、まずはご自身の自動車保険に弁護士費用特約が付帯しているかをご確認ください。弁護士費用特約がある場合には、一般的に300万円までであれば保険会社が弁護士費用を負担してくれますので、被害者が負担する弁護士費用はゼロとなります。死亡事故や重大な後遺障害が生じた事故を除けば、ほとんどのケースで弁護士費用は特約の300万円の範囲内に収まるはずです。
弁護士費用特約に加入している場合には、費用負担なく弁護士を依頼することができますので、弁護士に依頼をしたほうがよいケースだといえます。
5、まとめ
どんなに気を付けていたとしてももらい事故は避けられません。もらい事故の場合には、被害者に一切過失がない事故ですので、事故後の示談交渉などはすべて被害者自身で行わなければなりません。怪我の治療や日常生活を送りながら不慣れな示談交渉を行わなければならないというのは大きな負担となりますので、弁護士への依頼をおすすめします。
もらい事故の被害に遭ってお悩みのときは、ベリーベスト法律事務所 高崎オフィスまでお気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています