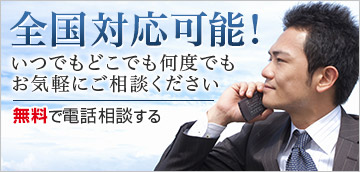【弁護士が解説】債権回収をスムーズに進める方法は? 誰に依頼すべき?
- 債権回収
- 債権回収
- 方法

平成30年の工業統計調査のデータによると、群馬県における平成29年6月1日時点での従業者数は20万9782人で、前年比2.3%の増加となっています。事業主にとっては、人件費の比率は大きく、取引先からの売買代金や請負代金の支払いが滞ってしまうと、資金繰りに大きな悪影響を及ぼしてしまいます。
少々の金額であれば自発的な支払いを待つとしても、未払いがある程度まとまった金額になってしまった場合には、しかるべき手段で債権回収を進めたいところです。
この記事では、債権回収をスムーズに進める方法や、債権回収の依頼先などについて、ベリーベスト法律事務所 高崎オフィスの弁護士が解説します。
(出典:「平成30年工業統計調査結果速報」(群馬県企画部統計課))
1、債権回収はどのように進めればよい?
まずは、債権回収を行うための具体的な方法としてどのようなものがあるかについて見ていきましょう。
-
(1)内容証明郵便などによる支払い催告
債権者が本腰を入れて債権回収を行う場合、まずは内容証明郵便などによる支払い催告を行うところから始めましょう。
内容証明郵便は、郵便局がその内容を記録・保管してくれる郵便の形式で、債権の正式な支払い催告を行うための方法としてよく用いられます。
内容証明郵便による支払い催告には、債権の消滅時効の完成を猶予する効果もあるため(民法第150条第1項)、早めの段階で送付しておくのがよいでしょう。 -
(2)裁判所による支払督促
内容証明郵便を送付しても、債務者が任意に債務を支払わない場合には、相手の住所地を管轄する簡易裁判所に対して支払督促を申し立てる方法もあります。
(参考:「支払督促」(裁判所ホームページ))
支払督促の申立てを行うと、裁判所の書記官による書類審査が行われます。
書類審査で債権が未払いになっている事実が認められた場合、裁判所から債務者に対して、債務を支払うようにという督促が行われます。
債務者が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議の申立てがない場合には、裁判所に申し立てることにより、支払督促に仮執行宣言が付されます。
この場合、債権者は仮執行宣言付きの支払督促に基づいて、強制執行の手続きを取ることが可能です。
支払督促は書類審査のみが行われるため、訴訟に比べて簡易な手続きであるというメリットがあります。 -
(3)訴訟提起・強制執行
支払督促に対して異議が申し立てられた場合には、自動的に訴訟手続きに移行します。
また債権者は、直接訴訟を提起することも可能です。
訴訟では、債権者と債務者が主張立証を戦わせ、債権の未払いがあるかどうかの事実認定が行われます。
債権者が勝訴判決を得て、その判決が確定した場合、債権者は確定判決の正本を債務名義として、強制執行の手続きを取ることができます。
2、債務者に任意の債権回収に応じてもらうための方法は?
債権者としては、債務者が任意に債務の支払いに応じてくれるに越したことはありません。
債務者に対して任意の債務支払いを促すために、債権者はどのようなことに注意すべきなのでしょうか。
-
(1)債務者にとって無理のない支払いスケジュールを提案する
債務者が債務を支払えないことの裏には、資金繰りが厳しいなどの事情があるのかもしれません。まずは債務者の話に耳を傾け、債務者がどのような状況にあるのかについて把握しましょう。
もし本当に資金繰りが厳しくて債務が支払えないという状況であれば、債務者にとって無理のない支払いスケジュールを提示することも有効です。
そうすれば、財務的な観点からも支払いが容易になりますし、債務者の心情的にも、債権者に対する恩義を感じて自発的な支払いを行う気になるかもしれません。 -
(2)支払わなければ法的手段に移行する旨を伝える
実際には、なかなか任意の支払いに応じない債務者が存在することも事実です。
その場合には、任意に支払わなければ法的手段に移行すること、その際の債務者にとってのデメリットを伝え、任意に支払うことのメリットを説明しましょう。
債務者としても、訴訟を提起されてしまうと対応に時間と労力を取られるため、訴訟を提起される前の段階で任意に支払っておこうという気持ちになるかもしれません。
3、裁判所に対して訴訟を提起して債権回収する際の注意点は?
債務者がどうしても任意の支払いに応じてくれない場合には、最終的には裁判所に対して訴訟を提起するほかありません。
以下では、裁判所に対して訴訟を提起して債権回収を目指す場合の注意点を解説します。
-
(1)民事保全法に基づく仮差押えを先に行う
債権回収のために訴訟を提起する場合、最終的には勝訴の確定判決を得て強制執行を行い、実際に金銭を回収することがゴールとなります。
しかし、仮に勝訴判決を得られたとしても、債務者の側に回収できる財産がなければ、訴訟は空振りに終わってしまいます。
このような事態を避けるために有効なのが、民事保全の手続きです。民事保全は、訴訟で勝った当事者が相手方からきちんと債権回収をできるようにするため、あらかじめ債務者の財産を処分されないようにしておくための制度です。
金銭債権の回収が訴訟の目的である場合は、「仮差押え」(民事保全法第20条第1項)という処分が行われ、債務者は仮差押えの対象財産を勝手に処分することができなくなります。 -
(2)債務者の財産を把握する
ただし、民事保全を行う前提として、仮差押えの対象となる財産を特定する必要があります。
つまり、債権者は債務者がどのような財産を持っているかを把握しておかなければ、民事保全の手続きを利用することができません。この点は、勝訴判決を得た後の強制執行の手続きについても同様です。
債務者の財産を調査するに当たっては、債務者の取引銀行や勤務先、取引先などを丁寧に調べていく必要があります。
4、債権回収を依頼できる専門業者とは?それぞれのメリット・デメリットを解説
債権回収を行う場合、内容証明郵便の送付や訴訟提起など、専門的な手続きを取る必要があります。
そのため、債権者が自分で債権回収に取り組むことには限界があると言わざるを得ず、債権回収を専門的に取り扱っている業者に依頼するのが賢明でしょう。
履行期限を過ぎた債権を回収する業務を、他人のために業として取り扱う行為は、当事者間に対立が生じている「法律事件」を取り扱うものと解されます。したがって、債権回収業務を取り扱えるのは、非弁行為の禁止規定により、原則として弁護士のみです(弁護士法第72条)。
ただし、債権回収に関する非弁行為の禁止には、「債権管理回収業者(サービサー)」と「認定司法書士」という2つの例外が設けられています。
債権管理回収業者(サービサー)、認定司法書士、弁護士のそれぞれに依頼をする際のメリットやデメリットについて見ていきましょう。
-
(1)債権管理回収業者(サービサー)
債権管理回収業者(サービサー)は、「債権管理回収業に関する特別措置法」(通称:サービサー法)に基づき、法務大臣の許可を得て債権管理回収業を営む株式会社です。
債権管理回収業者(サービサー)は、未払いとなっている債権を買い取ってくれる場合があります。その場合は、債務者から債権回収できるかどうかにかかわらず、債権者は現金を得ることができるメリットがあります。
しかし、取り扱うことのできる債権の範囲に限定がある上(債権管理回収業に関する特別措置法2条1項)、債権の買い取り時に大幅なディスカウントが行われるのが通常であり、債権者は額面どおりの金額を得られるわけではないことに注意が必要です。 -
(2)認定司法書士
認定司法書士とは、司法書士の中でも、少額訴訟などの小規模な紛争案件を取り扱う「簡裁訴訟代理等関係業務」を行うことについて、法務大臣の認定を受けた者をいいます。
認定司法書士に対する依頼費用は、弁護士への依頼費用と比べて安い傾向にあるというメリットがあります。
しかし、認定司法書士は訴額が140万円以下の事件しか取り扱えません。したがって、要回収額が140万円を超える場合には、認定司法書士に依頼することはできないことに注意が必要です。 -
(3)弁護士
弁護士は、要回収額の多寡にかかわらず債権回収業務を取り扱えるため、債権回収業務全般を任せることができます。
また、弁護士は法的知識を備えており、裁判所での手続きにも精通しているため、依頼者が置かれている状況に合わせた適切な債権回収の戦略を立てることが可能です。
依頼費用は認定司法書士よりも高額になる傾向がありますが、充実したサポートの対価と考えれば、あながち不合理とはいえないでしょう。
5、まとめ
債権回収は法的・専門的な手順を踏んで行う必要があるため、債権者がご自身だけで取り組むのは非常に困難です。
債権回収の依頼先には債権管理回収業者(サービサー)・認定司法書士・弁護士の3つがありますが、総合的に考えれば、弁護士に依頼するメリットが大きいといえるでしょう。
ベリーベスト法律事務所では、債権回収の専門部署を構え、日々債権回収案件の対応を行っております。その蓄えたノウハウを生かして、速やかな債権回収を実現するよう尽力いたしますので、債権回収についてお悩みの方は、ぜひ一度ベリーベスト法律事務所にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています