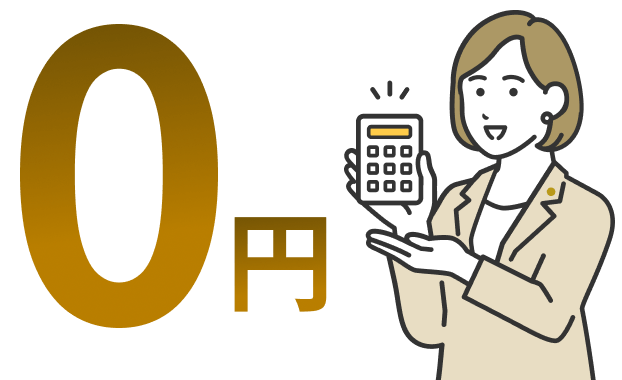確実に相続させるためには? 効力のある遺言書の書き方を徹底解説!
- 遺言
- 遺言書

超高齢化社会となった昨今、全国的に遺産相続のトラブルが増えています。たとえば、群馬県内を管轄する前橋家庭裁判所における遺産分割事件数は、平成12年では142件、平成29年が174件と、増加傾向がみられます。全国規模でも、平成12年では年間8889件、平成29年には12166件と、大幅に増加しているのです。
親しかった親族が、あなた自身が亡きあと、あなた自身の遺産を巡って争いになり、疎遠になってしまうことほど悲しいことはありません。そのような事態を避けるためには、遺言書の作成は大変有効です。
遺言書とはどのようなものか、どのような手続きが必要なのかについて、解説します。
1、遺言書の意義と用語
遺言書を作成する前に、遺産相続の関係者を指す用語と、遺言の意義を確認しておきましょう。
-
(1)被相続人、相続人とは
「被相続人(ひそうぞくにん)」とは、相続可能な財産を遺して亡くなった方を指します。そして「相続人(そうぞくにん)」は、被相続人が遺した財産を受け取る権利を持つ者です。相続は、被相続人の死亡により、はじまることになります。
-
(2)法定相続とは
相続人に該当する者は、民法によって定められています。被相続人が亡くなった場合、遺言書がなくても、相続が開始します。遺言書がないケースでは、原則として、民法に規定された「法定相続」に従って、相続が進むことになります(民法第900条)。
しかし、遺言書がないケースでは、現金・預貯金、株式、家・土地など全ての遺産につき、誰がどう取得するのかを、相続人がゼロから話し合わねばなりません。この協議は「遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)」と呼ばれるものです。遺言書がなく、被相続人による指針がない状態での遺産分割協議は相続人間の争いの元となりえます。また、相続人にとって大変負担の大きい作業といえるでしょう。 -
(3)遺言書を作成するメリット
被相続人が、法的に有効な「遺言書」を作成しておけば、その内容については「法定相続」より優先して適用されます。具体的には、遺言書の作成によって、自分の財産を、自分の意思で、誰に、何を、どのような割合・方法で相続させるのかをあらかじめ決めておくことができるのです。
たとえば、生前とてもよく介護をしてくれた親族に多く財産を分けることや、血縁関係のない人に財産を分けることもできます。また、自分のコレクションを価値のわかる友人や機関に遺すことも可能です。
自分の遺志をしっかりと示し、相続における親族間の争いを避け、スムーズな相続手続きに備えた最大限の配慮といえるでしょう。
2、遺言書の種類、書き方、特徴
遺言書と一口にいっても、いくつか種類があるのをご存じでしょうか。
遺言が効力を発生する時点で、書いた本人である被相続人は当然亡くなっているため、遺言に曖昧な記述や不明確な部分があったとしても、真意を確かめることができません。そこで、遺言の解釈で無用な混乱が生じるのを避けるために、遺言書の方式や効力、手続などを民法第960条から第1027条において、詳細に定めています。
なお、近年の相続に関する諸問題に対応するため、平成30年7月に法改正が実現し、遺言書の作成に関する規定変更なども行われています。施行日が平成31年度中になるため、相続が発生した日、および遺言書が書かれた日によって、適用される法律の内容が変わる可能性がある点にも注意が必要です。
遺言書は種類によって書き方も特徴も異なっていますから、ご自分の遺志を全うできるよう、適切な種類の遺言状を選ぶようにしましょう。
-
(1)自筆証書遺言
一般的に行われることが多いのが「自筆証書遺言」(民法第968条)です。自筆証書遺言とは、遺言者本人が、内容と、日付および氏名を自筆し、押印することで成立します。
自筆証書遺言は、証人を用意する必要がないため、いつでもどこでも紙とペンと印鑑があれば手軽に作成できます。誰にも見られず書くことが可能ですから、秘匿性が高いものです。しかし、あくまでも自筆で行われることが必要であるため、原則として、パソコンなどで入力し印刷したものでは認められません。もっとも、2019年1月13日、改正された法律が施行され、財産目録など一部のみパソコンなどで入力した書類や通帳のコピーなどの添付などが認められるようになりました。なお、自書しない財産目録などについては、各ページに、署名押印などが必要になります。詳細は弁護士など専門家にアドバイスを受けることをおすすめします。
また、自筆証書遺言では、相続を開始するときに大事な手続きがあります。遺言書の保管者や遺言書を発見した相続人は、家庭裁判所に対し正しい遺言の方式で記載されているか確認を求める「検認」の手続きを請求しなければなりません(民法第1004条第1項)。検認を経ずに勝手に開封した場合、「過料(かりょう)」に処されることになりますので、注意しましょう(民法第1005条参照。)。
またこの遺言書は自分で保管することになるため、紛失したり、改ざんされたりする可能性があることも忘れてはいけません。作成や保管については、弁護士のアドバイスを受けることをおすすめします。 -
(2)公正証書遺言
「公正証書遺言」(民法第969条)とは、公証人が、法律で定められた方式に従って作成する遺言です。
公正証書遺言の作成には、2人以上の証人の立ち合いが必要です。2人以上の証人を連れて公証役場へ行き、遺言書を書く本人が遺言の内容を伝え、公証人が記述します。自筆証書遺言と比べてやや手間と費用がかかりますが、専門家である公証人が作成するため、形式不備による無効の心配がありません。
また、原本は公証役場で保管されるため、紛失のおそれもありません。公証手続きを経ているため、相続開始後の検認手続も不要です(民法第1004条第2項)。
公正証書遺言の場合、仮に遺言者が署名することができない場合には、公証人がその旨を記載すれば、署名に代えることが可能であるため、身体に不自由がある場合にはこの方法で遺言書の作成が可能になります(民法第966条第4号但書参照。)。
ただし、被相続人も、誰にどのような財産を相続させるかといった遺言の内容自体は自身で考えたうえで、公証人と打ち合わせをする、関係書類をそろえるといった準備が必要になります。公正証書遺言の作成についても、弁護士などの専門家に、事前の相談や依頼をしたほうがよいといえるでしょう。 -
(3)秘密証書遺言
「秘密証書遺言」(民法第970条)とは、自筆証書遺言と公正証書遺言の間をとった遺言といえます。作成方法は、遺言者が、遺言を作成してそれに署名押印し、これを封筒に入れて遺言書に押印した印鑑と同じ印鑑を用いて封印し、その封筒を公証人と証人2人の前に提出して、公証人に認証してもらいます。公正証書遺言と同じく2人以上の証人を自分で用意しなくてはなりませんが、こちらは遺言書の内容を知られることはないため遺言の秘密は確実に保持できます。
しかし、遺言書作成時に内容の確認ができないため、開封時は家庭裁判所の検認が必要です。自筆証書遺言と同様に、検認を経ずに勝手に開封した場合、「過料」が科されます。また、自筆証書遺言の場合と同様、紛失のリスクがあります。
なお、検認の際に形式上の誤りが発覚し、無効になってしまうことも少なくないようです。せっかくの遺言が無効になっては、自分の意思に沿わない相続になってしまう可能性が高まります。やはり、この場合も、弁護士などの専門家へ、事前に相談したほうがよいでしょう。内容を話すことに不安を感じられるかもしれませんが、弁護士であれば守秘義務がありますので、相談の内容を漏らすことはありません。 -
(4)特別方式遺言
特別方式遺言(民法第976条等)は、死期が迫っているような状態であるときに迅速かつ簡易な方法により遺言書を作成することが認められる特別な方式です。特別方式の遺言は、それぞれ危篤のとき、遭難したとき、伝染病で隔離されているとき、船上にいるときの例外的な場合に認められる遺言です。そのため、実際に利用されるケースはほとんどありません。なお、特別方式遺言をした場合であっても、遺言者が普通方式の遺言書ができるようになってから6ヶ月生存した場合は、効力を失います(民法第983条)。
3、遺言書において指定できる事項
遺言書は、「どのような内容でも書き遺せば法的な効力を持つ」というわけではありません。
遺言によって法的な効力を持たせることができる事項は、大まかに分類すると「財産に関すること」「遺言の執行に関すること」「身分に関すること」の3種です。
-
(1)財産に関すること
相続分の指定(民法第902条)、遺産分割の方法の指定(民法第908条)、特別受益の持戻しの免除(民法第903条第3項)、相続人相互の担保責任の指定(民法第914条)、遺留分減殺方法の指定(民法第1034条但書き)などを行うことが可能です。
また、誰かに財産を無償で与える「遺贈」、財団法人設立のための「寄付」、そして「信託の設定」を行うことができます。 -
(2)遺言の執行に関すること
相続の手続きを行う「遺言執行者の指定・委託」(民法第1006条第1項)、ができます。
「遺言執行者」とは、土地の登記名義や銀行口座の名義変更といった、相続に必要不可欠となる事務手続きを行う者です。遺言執行者は、家族だけでなく、弁護士を指定することもできます。ただし、未成年の子どもや破産者などは指定できません(民法第1009条)。 -
(3)身分に関すること
「認知」(民法第781条第2項)、「未成年後見人・未成年後見監督人の指定」(民法第839条第1項等)など、遺された家族の身分に関することを指定することができます。
被相続人に、生前は認知できなかった子どもがいて、その子どもにも相続させたいときなどは、遺言によって「認知」するよう指定できます。認知された子どもは法定相続人となり、財産を相続する資格を得ることができます。また、被相続人が亡くなることによって親権者がいなくなる子どもがいる場合には、未成年後見人の指定もしておくことができます。
法律で定められたこれらの「遺言事項」以外は、遺言書に記載しても法的な効力はありません。しかし、なぜそのように相続するよう指定をしたのかなどを付記することによって、より円満な相続となる可能性があるでしょう。
4、遺言書が法的に無効になってしまうケース
作成した遺言書全体が、残念ながら法的には無効だったというケースは少なくありません。無効となる遺言書を作成しないためには、登記情報など自らの財産内容を改めて洗い出して正確に書き写すなどのほかに、遺言を書く人つまり被相続人の状態に関する、3つのポイントがあります。
-
(1)遺言書を有効に作成できる能力・状態にあるか
遺言の作成には、被相続人自身の意思能力が必要です。具体的には、通常人としての正常な判断能力、理解力、表現力を備え、遺言内容について十分な理解力を有していることが必要です。たとえば、認知症の状態で書いたとする遺言書は無効とみなされる可能性が高まります。
なお、成年後見人が就任している成年被相続人については、一時的に自身の意思能力や判断力が回復したときに、2名以上の医師の立ち合いなどによって作成した遺言書の効力が認められます(民法第973条参照。)。
また、被相続人は、満15歳以上である必要があります(民法第961条参照。)。幼過ぎると自分の財産の処分を適切に判断できないとみなされ、遺言は無効となります。 -
(2)法で定められた作成手順が守られているか
遺言書に法的な効力を持たせるためには、法で定められた作成手順でなければ無効となります。
具体的には、以下のような不備で法的な効力が無効となるケースがあります。- 自筆証書遺言が本人の手書きでない(例外的にパソコンでの印刷、コピーを使用できる場合を除く。)
- 日付が「○年○月吉日」などになっており、特定できない
- 押印の印影が、封緘(ふうかん)と本文で違う
- 公正証書遺言、秘密証書遺言の証人の身分が不適格だった(民法974条)
- 記載されている財産額と現実の財産額がかけ離れている
なお、公正証書遺言や秘密証書遺言で求められる「証人」には、民法によってその範囲が定められています。具体的には、「未成年者」「推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族」「公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人」は証人または立会人になることができません(民法第974条各号参照。)。もし、証人を依頼できる人物がいなければ、公証役場や弁護士に依頼することが可能です。
書式、手続きについては、弁護士に、確認することをおすすめします。 -
(3)遺言書の作成に本人以外が関わっていないか
まず、偽造された自筆証書遺言は当然ながら無効となります。本人の意思が適切に反映されたものではないためです。
また、民法第975条では、「2人以上が同一の書面で遺言を作成することはできない」と定められています。たとえば、夫婦連名による「共同遺言」は、法的には無効になります。
5、まとめ
不備のない遺言を作成することは、あなたにとっても、あなたの家族にとっても非常に大きなメリットがあるでしょう。トラブルは財産の多寡にかかわらず発生することがあります。検討する価値はあるのではないでしょうか。
なお、遺言書作成は、専門的な知識やサポートが必要となる可能性が高い作業でもあります。特に相続法に関連する分野は、平成30年に法改正が行われ、平成31年に施行が控えている状態です。常に最新の状況をキャッチアップしている弁護士のアドバイスを受けることで、適切な遺言書を作成できるでしょう。
遺言を作成するにあたっては、前提として財産の洗い出しが必要となります。まずは、ベリーベスト法律事務所・高崎オフィスへ相談してください。ベリーベスト法律事務所であれば、必要に応じて、税理士や司法書士などの他士業をご紹介することが可能です。遺言書の作成から、生前分与、相続税対策など、相続に関して、専門家同士で連携し、多角的な対応を実現します。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
- |<
- 前
- 次
- >|